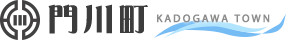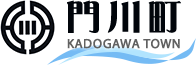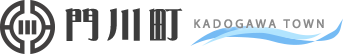門川町統計書(沿革)
町の沿革
門川町の藩制時代は延岡藩に属し、大字門川尾末に大庄屋を置き、宇納間村、黒木村、入下村、川内村、門川尾末村の5ヶ村を統括して、門川組と称したが、庵川村と加草村は恒富組に属した。明治12年12月、加草村と庵川村の戸長役場が加草村に、門川尾末村と川内村の戸長役場が門川尾末村に設置された。
明治17年1月、臼杵郡は、東臼杵郡と西臼杵郡に分けられ戸長役場の管轄が拡大された。その結果、門川尾末村、加草村、庵川村、川内村の戸長役場が門川尾末村に置かれた。
その後、明治22年4月、町村制が実施された際、前記4ヶ村を合併して門川村となる。そこで千田ノ木に役場庁舎を建築し、開庁と同時にそれまでの戸長、副戸長、里正の名称は、村長、助役、収入役と改め、議決機関として初めて村会議員が村民より選出された。
つづいて大正12年、本町に木造2階建の役場が新築された。以後、村政は、日豊本線の開通など文明の光を受け、順調な発展を続け、昭和10年2月11日に町制が施行され門川町となった。当時の世帯数2,289世帯、人口11,684人であった。
役場所在地
宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号
位置
| 役場所在地 | 門川町( 極所 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経緯度 | 方位 | 経度 | 方位 | 緯度 | |||
| 東経 | 131゜38'47" | 極東 | 東経 | 131゜43' | 極南 | 北緯 | 32゜26' |
| 北緯 | 32゜28'15" | 極西 | 東経 | 131゜30' | 極北 | 北緯 | 32゜32' |
主な山岳 (m)
| 名称 | 標高 |
|---|---|
| ニクシ山 | 692 |
| 駒瀬山 | 652 |
| 唐松山 | 428 |
| 遠見山 | 308 |
主な河川(km)
| 名称 | 延長 |
|---|---|
| 五十鈴川 | 約 41 |
| 鳴子川 | 約 4 |
ばく布(m)
| 名称 | 所在地 | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|
| 津々良の滝 | 大字川内 | 30 | 8 |
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
地域振興課 にぎわい創出係 TEL:0982-63-1140(内線2223,2224) メールによるお問い合わせは こちら |