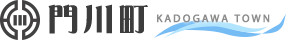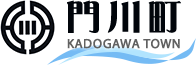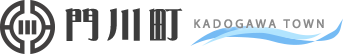国民健康保険のしくみ 届出ほか(届出が必要なとき)
国民健康保険(国保)とは
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療機関にかかれるよう、加入者みんなでお金を出し合って医療費に備える制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が国保に加入します。
国保の届け出が必要なとき
国保に加入するとき、国保をやめるときは、14日以内に届け出が必要です。下記のような場合は、門川町役場の国保の窓口(⑤番窓口)まで届け出を行ってください。
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に入るとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
| 職場の健康保険などをやめたとき | 健康保険をやめた証明書 (加入前に確認) 退職日の翌日から2年間職場の健康保険を継続できる制度があります。世帯状況によっては、保険料が国民健康保険に加入するより低額の場合があります。20日以内の手続きが必要なため、あらかじめ勤務先にご相談ください。 |
|
| 健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | マイナンバーカード・資格確認書・母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国籍の人が国保に加入するとき | 在留カード、パスポート | |
| 国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | マイナンバーカード・資格確認書 |
| 職場の健康保険などに加入したとき | マイナンバーカード、国保と健康保険の両方の資格確認書・資格情報のお知らせ (または加入したことの証明書) |
|
| 健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき | マイナンバーカード・資格確認書・印かん (様式)葬祭費申請書 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | マイナンバーカード・資格確認書・保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の人が国保をやめるとき | マイナンバーカード・資格確認書・在留カード | |
| その他 | 町内で住所が変わったとき | マイナンバーカード・資格確認書 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | マイナンバーカード・資格確認書 | |
| 世帯が分かれたりいっしょになったとき | マイナンバーカード・資格確認書 | |
| 修学のため町外に転出したとき | マイナンバーカード・資格確認書・在学証明書 | |
| 資格確認書をなくしたとき(再交付) | 身分を証明するもの |
※上記の届け出に必要なもののほかに、「世帯主」と「手続きの対象となる人」のマイナンバー、本人確認ができるものと、保険税の口座振替や払い戻しの際に使用する「世帯主」の通帳、通帳の届出印をお持ちください。
資格確認書(資格情報のお知らせ)
資格確認書(資格情報のお知らせ)は国保の加入者である証明書であり、お医者さんにかかるときに必要となるものです。1人に1枚交付されますので、大切に保管しましょう。
有効期限を過ぎた資格確認書(資格情報のお知らせ)については、窓口に返還をするか、ご自身で裁断する等、確実に破棄して下さい。また、有効期限を過ぎた資格確認書(資格情報のお知らせ)は利用できません。使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費を返還する場合があります。
医療機関にかかるとき
医療機関の窓口でマイナンバーカード・資格確認書を提示すれば、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。自己負担割合は、年齢と所得で異なります。
自己負担割合
| 小学校入学前 | 2割 | |
|---|---|---|
| 小学校入学後69歳まで | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | ||
| 一般、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ | 2割 | |
| 現役並み所得者 | 3割 | |
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
| 住民税課税世帯 | 510円 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 過去 12か月の 入院日数 |
90日までの入院 | 240円 |
| 低所得者Ⅱ | 90日を越える入院(要申請) | 190円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | ||
※やむをえない理由により認定証を使用しなかった場合には、差額支給ができます。ただし、緊急入院などであり、認定証を知らなかったなどの理由は該当しないのでご了承下さい。
過去12ヶ月間で延べ91日以上の入院となった場合は、証明できる領収書等の書類を持参のうえ、長期入院該当の手続きをしてください。申請以降の適用になります。過去の分に遡っての適用はできません。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
| 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 |
|---|---|
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人。 |
| 低所得者Ⅱ | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰを除く)。 |
| 低所得者Ⅰ | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。 |
医療費が高額になったとき
1か月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は年齢、所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
※国民健康保険税を滞納している人には、限度額適用認定証は交付されません。
平成30年4月から高額療養費の多数回該当の引継ぎが県単位になりました。
高額療養費の自己負担限度額判定の際、未申告の場合、上位所得者として取り扱われます。
申告がお済みでない方は、早めに申告してください。所得税や町・県民税(住民税)の申告が必要ないといわれた所得金額の人でも必要です。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 所得901万円超 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 所得600万円超 901万円以下 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 所得210万円超 600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
同じ人が同じ月内に同じ診療機関で支払った自己負担額(食事代やベッド代等の保険対象外は含まない)が超えた場合、その超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【4回目以降:140,100円】 |
|
| 現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【4回目以降:93,000円】 |
|
| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【4回目以降:44,400円】 |
|
| 一般 | 18,000円 | 57,600円 【4回目以降:44,400円】 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※外来の限度額を適用後に、外来+入院の限度額を適用します。
国民健康保険税
国民健康保険税は、国保制度を支えるための大切な財源になります。保険税は、国保加入者の所得や人数などに応じて世帯単位で決まります。世帯主本人が国保の加入者でなくても、世帯の中に一人でも国保の加入者がいれば、保険税の納付義務者は世帯主となります。
なお、理由なく保険税を滞納すると督促が行われ、延滞金などが加算されます。また、高額療養費の限度額適用認定を受けられません。さらに、資格確認書等を返還していただき、医療費がいったん全額自己負担となる「資格確認書(特別療養)」が交付され、国保の給付の全部または一部が差し止めになることがあります。
保険税は、納期限までに納付していただきますようご協力をお願いします。
※国民健康保険税は、原則として口座振替で納付していただきます。門川町指定の金融機関で口座振替の手続きを行ってください。
申告がお済みでない方は、早めに申告してください。所得税や町・県民税(住民税)の申告が必要ないといわれた所得金額の人でも必要です。
申告をしていない場合は、税の軽減の適用を受けれなかったりと不利益が生じる場合があります。
会社都合により失業した方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)については、保険税が安くなる可能性があります。手続きの際には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります。
災害(震災、風水害、火災等)による国民健康保険税の減免
震災、風水害、火災等で被災された被保険者の方は、申請していただくことにより、国民健康保険税を減免できる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
医療費は大切に
医療費が年々増え続けています。日頃から健康づくりを心がけるとともに、医療費の節約にご協力をお願いします。
- 生活習慣病の原因である内臓脂肪の蓄積の早期発見や早期改善を行うために、国保さわやか健診(特定健診)を毎年受診しましょう(40歳以上の人が対象となります)
- 緊急時を除いて、休日や夜間の時間外受診は控えましょう
- かかりつけ医を持ち、気になることがあればかかりつけ医に相談しましょう
- 医師の紹介状なしに、同じ病気で複数の医療機関にかかるのは控えましょう
- 薬のもらいすぎには注意しましょう
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)を積極的に利用しましょう
交通事故などで医療を受けるとき
交通事故や傷害など、第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
この場合、加害者が支払うべき医療費を門川町国保が一時的に立て替え、あとで加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。
そのため、国民健康保険を使って治療したときは、国保窓口へ被害の届け出が義務付けられています(国民健康保険法施行規則第32条の6)。
詳しくは宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
<届出に必要なもの>※様式は、下記の宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードをお願いします。
・第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書
・交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センター発行)
・門川町国保の被保険者であることを確認できる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
・印かん
<様式ダウンロードページ>
宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>
| お問い合わせはこちら |
|---|
|
町民健康課 医療保険係 TEL:0982-63-1140 メールによるお問い合わせは こちら |